今年は本当に自然災害が多いですね。
この原稿を書いているときにも、北海道の地震がテレビで多く報道されています。
家づくりと災害は密接につながっています。
そこで、今回は西日本豪雨について報告します。
西日本豪雨は、200人以上が亡くなった大きな災害となりました。
あの報道を見て、鬼怒川が氾濫した事を思い出した方も多かったのではないでしょうか。
51人が亡くなった岡山県倉敷市真備町。
この地区では、16年に倉敷市が作成したハザードマップで「洪水時に2階の軒下以下が浸水する程度の危険性」があると指摘していました。
2階の軒下の高さというと6mを超えてしまう高さです。
2階の屋根下まで水が来るかもしれないと言われていたことになります。
実際には5mくらいだったそうですが、それでも2階の窓半ばくらいの高さです。
これらの事から、ハザードマップが有効だったと言われています。
この地区の雨に対しては、東大の芳村准教授は「1400年に1度の多さだった」と言っています。想定を上回る事も有りそうです。
「100年前にも洪水があったという石碑があったのに、誰も気にしていなかった」という話も聞きました。
先人が残してくれた大切な石碑をおろそかにしない事も必要です。
気になるのは「猛烈な雨」が増えていることです。
1976年からの10年間と、2008年からの10年間では1.6倍に増えています。
猛烈な雨は、想定を大きく超え始めています。
インフラや行政が命を守ってくれると楽観視する事は危険です。
地域や個人単位で命を守る防災を考えておく必要があります。
そこで、避難を最優先にする事が大切です。
真備町では亡くなった方の8割が70歳以上だったそうです。
高齢者や小さな子供がいる家族で、周りの人に迷惑になるからと避難しなかった方もいたと聞きましたが、まずは自分と子供の身を守る事を優先させましょう。
参考文献:日経アーキテクチャー2018:8-9

+α ―ハザードマップー
「ハザードマップ」という言葉は知っていても、実際に見た事がある方は少ないのではないでしょうか?
ハザードマップとは、洪水などがおきたときに浸水する地域を示している地図です。
現在、ハザードマップは各市町村のHPで簡単に見る事ができます。
自分の住んでいる地域がどのような地域なのか、確認しておいてくださいね。
新しい土地を購入するときには、ハザードマップを見て確認しておく事も大切ですよ。

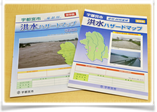


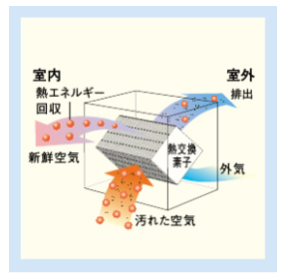
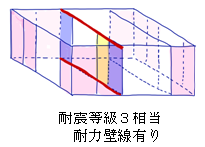

コメント